令和6年1月からマイナンバーカードとe-Taxで確定申告・還付申告が大幅に便利になります。
特に「マイナンバーカード」があれば、スムーズに申告が行えるようになりますので、まだ取得されていない方は、早めに取得の手続きを完了させてください。
マイナンバーカードの取得方法やスマートフォンを利用した申告の方法は以下の記事でご紹介させて頂いております。
合わせてご参照ください。
今回は「確定申告・還付申告」の概要についてご紹介させて頂きます。
毎年申告されている方は、手続きの方法等に慣れていらっしゃると思いますが、今年、初めて確定申告・還付申告をされる方や、久しぶりに行う方には、どのように手続きをしたら良いか分からないことだらけだと思います。
また、少し分かりにくい、「確定申告と還付申告」の違いについてもご説明させて頂きます。
誰でも簡単に確定申告・還付申告が出来るように、必要書類や提出の仕方、提出期限などについて簡潔に詳しくご紹介させて頂きます。
ぜひ、確定申告の際のご参考にしてみてください。
なお、今回は、個人の確定申告のみを対象としております。
法人に関しては、必ず税理士等とお打ち合わせをしてください。
確定申告とは
確定申告
提出年度、前年の1月1日から12月31日までに得た所得を計算して、申告書として税務署に申告することを言います。
所得基準を超えた場合は、所得税として納税をする必要があります。
個人事業主等の課税事業者であれば、消費税を納める必要があります。
源泉徴収を行った金額が、実際の所得税額よりも多かった場合は、還付を受けることが出来ます。
提出期間
2024年2月16日(金)~2024年3月15日(金)
(個人事業主の消費税・地方消費税は2024年4月1日(月)まで)
提出方法・提出場所
- 税務署(申告時点でお住まいの地域の)へ持参または郵送
- e-Taxで申告
郵送で提出される場合は信書扱いになりますので、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストは利用出来ませんのでご注意ください。
確定申告書に関する相談を希望する場合、入場整理券が必要ですのでご注意ください。
詳しくは下の記事でご紹介させて頂いております。
還付申告とは
還付申告
「還付申告」とは予定納税や源泉徴収などで、事前に納めた所得税が、本来納めるべき税額よりも多く支払っている場合、確定申告することにより「還付」を受けられることを言います。
提出期間
翌年の1月1日から5年間。
提出方法・提出場所
- 税務署(申告時点でお住まいの地域の)へ持参または郵送
- e-Taxで申告
確定申告 必要な人
個人事業主・自営業の方
所得額が48万円以上の方は確定申告をする必要があります。(控除前)
会計ソフトなどを使用しご自身で申告書を作成するか、税理士等にお願いするようにしましょう。
銀行等の金融機関から借り入れ等がある場合は、確定申告書が必ず必要になりますので、忘れずに申告するようにしてください。
控除後の所得が0円以下であれば申告の義務はありません。
しかし、どのような状況であっても、確定申告をしておくことをお勧めします。
確定申告をするかしないかで、赤字の繰越や年金等にも大きな影響がありますので、事業を行っている間は売上の大小、所得の金額に関わらず、必ず毎年確定申告を行ってください。
会社員(サラリーマン)の方
- 給与が2000万円を超える方
- 給与以外に他の所得が20万円を超える方
- 給与を2箇所以上から受けている方(副業等を含む)で年末調整をされていない所得が20万円を超える方
副業や金融関連の利子・配当等が20万円を超える方・超えそうな方で、ご自身が確定申告をするかどうかご不明な方は、早めに税務署・税理士にご相談されるようにしてください。
副業をされている方
申告している所得以外に、20万円を超える所得がある方は、基本的に確定申告の必要があります。
株式投資などの金融取引を行われている方はご利用の証券会社等の申告に関する手引き等を良くお読みください。
特定口座やNISA口座、先物取引、FXなどそれぞれ取り扱いが違います。
アフィリエイトなどを行われている方も同様に、ご利用のASP等の申告に関する手引き等をお読みください。
年金を受給されている方
- 公的年金の収入が400万円を超える方
- 年金以外の所得が20万円を超える方
還付申告をしたほうが良い方(税金が戻ってくる方)
退職された方
年度の途中で退職された方で、かつその年度内に再就職しなかった方。
医療費控除を受ける方
1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。
この場合の医療費は、病院等に支払った金額だけでなく、交通費等も対象になりますので、領収書等は大事に保存しておいてください。
(所得が低い方は、総所得金額等の5%を超える場合申告することが出来ます)
ふるさと納税をされている方
ふるさと納税ワンストップ特例に該当する方は、確定申告をする必要はありません。
但しふるさと納税先が6件以上の方や、他の要件で確定申告をする場合は、申告する必要がある場合があります。
寄付をされた方
特定の団体に寄付をされた方は控除を受けることが出来ます。
寄付先にその旨の記載があると思いますので、確認してください。
自然災害等に遭われた方
自然災害等に遭われた方は控除を受けることが出来る場合があります。
特に住宅等の生活必需品が被害にあった方は控除の対象となります。
対象となるものの判別が難しい場合もありますので、各自自体、税務署、税理士に相談してください。
住宅ローン控除
個人で住宅を新築、増改築した場合、一定の要件を満たすと控除を受けることが出来ます。
また省エネ、バリアフリーに関する改修を行った場合も控除を受けることが出来る場合があります。
一度申請すれば、2年目以降は年末調整で対応出来ます。
書類が多数必要となりますので、早めに準備しておくことをお勧めします。
住宅ローン控除については以下で詳しくご紹介させて頂いております。
控除を受けられる可能性がある方
年末調整後に保険料を支払ったり、保険に加入したりした方、また家族構成に変更があった方などは還付申告をすることにより還付金を受け取ることが出来る場合があります。
該当する可能性がある場合は、税務署等で相談してください。
確定申告・還付申告 必要書類
本人確認書類
以下、①、②のどちらか。
①マイナンバーカード(写しによる確認の場合は、表面及び裏面の写しが必要)
②マイナンバーが記載された通知カード、または住民票(番号確認書類)
身元確認書類:運転免許証、パスポート等(身元確認書類)
扶養者や、専従者等がいる場合は、その方のマイナンバーが分かるものも必要となります。
印鑑
作成した書類に押す印鑑(シャチハタ不可)
自宅で作成して捺印しておけば持参する必要はありません。(但し万が一の訂正等も考慮して持参するのが良いと思います)
e-Taxを利用される方は必要ありません。
確定申告書
確定申告書A・確定申告書Bのどちらかが必要となります。
確定申告書A:給与所得者
確定申告書B:個人事業者(フリーランス等)
基本的には、Aは2枚、Bは4枚綴りになります。
確定申告書Aに該当する方が、Bを使用しても問題ありません。
所得証明書
源泉徴収票(給与、年金)、青色申告決算書、その他取引計算書や売買契約書等。
書類は申告される方により違いがあります。
控除証明書
医療費控除、社会保険料控除、共済等掛金控除、生命保険料控除、住宅ローン控除、寄付控除などにより必要書類は変わります。
預貯金口座番号が分かるもの
税金の還付を受ける予定のある方は、通帳等の口座番号が分かるもの
昨年分の申告書等の控え
前年に確定申告をされた方は、その控えを持参するように国税庁のホームページに記載されております。
あくまでも個人的な経験ですが、長年の確定申告の中で、提示を要求されたことは一度もありません。
申告手続きの流れ
初めて確定申告をされる方や、久しぶりに確定申告を行う方は、手続き等が複雑に感じるかもしれません。
しかし、事前の準備をきちんとしておけば、意外とスムーズに申告出来ますので、ご自身の状況に合わせて一つずつクリアして行ってください。
①必要書類の準備
先程ご紹介させて頂いた源泉徴収票や各種控除証明書等を準備します。
②申告書を作成する
国税庁のホームページに申告書の作成方法が記載されております。
状況に応じて、用意する書類が異なる場合もありますので、注意してください。
申告書作成コーナーの使い方については以下にて詳しくご紹介させて頂いております。
合わせてご覧ください。
③提出書類の確認
出来上がった申告書と添付する必要のある書類の再確認です。
控除する分野で必要書類が変わりますので注意してください。
また、添付する書類は申告書の裏面等に貼らずに、専用の台紙に貼るようにしてください。
以下国税庁の添付書類台紙になります。
④申告書の提出
確定申告の場合は、3月15日までに、最寄りの税務署に持参、または郵送、あるいはe-Taxで申請してください。
(郵送する場合は、「信書」扱いになりますので、郵便局からのみの配送となります)
⑤納税、または還付を受ける
税務署へ持参する場合は、その場で納付することが可能です。
または納付書を使用して金融機関で後日振り込むことも可能です。
e-Taxを利用される方はダイレクト納付が可能です。
(事前の登録等が必要です)
その他、電子納税やクレジットカード払い(手数料有り)、コンビニ払いなどがあります。
納税について詳しくは別記事でご紹介させて頂きます。
提出期限を過ぎた場合はどうする?
確定申告の提出期限は毎年3月15日までと決められていますが、万が一提出期限に間に合わなかった場合はどうしたら良いでしょうか。
何らかの理由で期限までに提出出来なかった場合は、速やかに税務署へ行って確定申告書を提出するようにしましょう。
僅かな遅れであれば、特に罰則もなく受理してもらえると思います。
但し、日数が経ちすぎている場合や、悪意のある場合などは、加算税・延滞税を課せられることもありますので、十分に注意してください。
(お忙しい中大変だとは思いますが、なるべく指定された期日までに提出するようにしましょう。ご自身で作成するのが大変な場合は、迷わず税理士等に相談するようにしてください。)
提出した申告書に誤りがあった場合
提出した確定申告書に誤りがあった場合は、更正の請求書、修正申告書の提出を行うようにしてください。
また令和5年分の確定申告書で、すでに提出した場合は、再度確定申告書を提出してください。
どちらの申告書も確定申告書作成コーナーから作成することが出来ます。
まとめ
いかがでしたか。
簡単ですが、「確定申告・還付申告」の手続きについてご紹介させて頂きました。
税務署での相談を希望される場合、入場整理券が必要など、例年とは違った対応が求められるケースがあります。
なるべく早めに必要書類を準備して、申告に必要な書類を揃えておくことをお勧めします。
記載させて頂いた情報は、十分に調べた上で記載させて頂いておりますが、内容の正確性を保証するものではありません。
ぜひ今回の記事を皆様の確定申告の際のご参考にして頂いて、ご不明な点は、最寄りの税務署、または税理士等にご相談ください。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

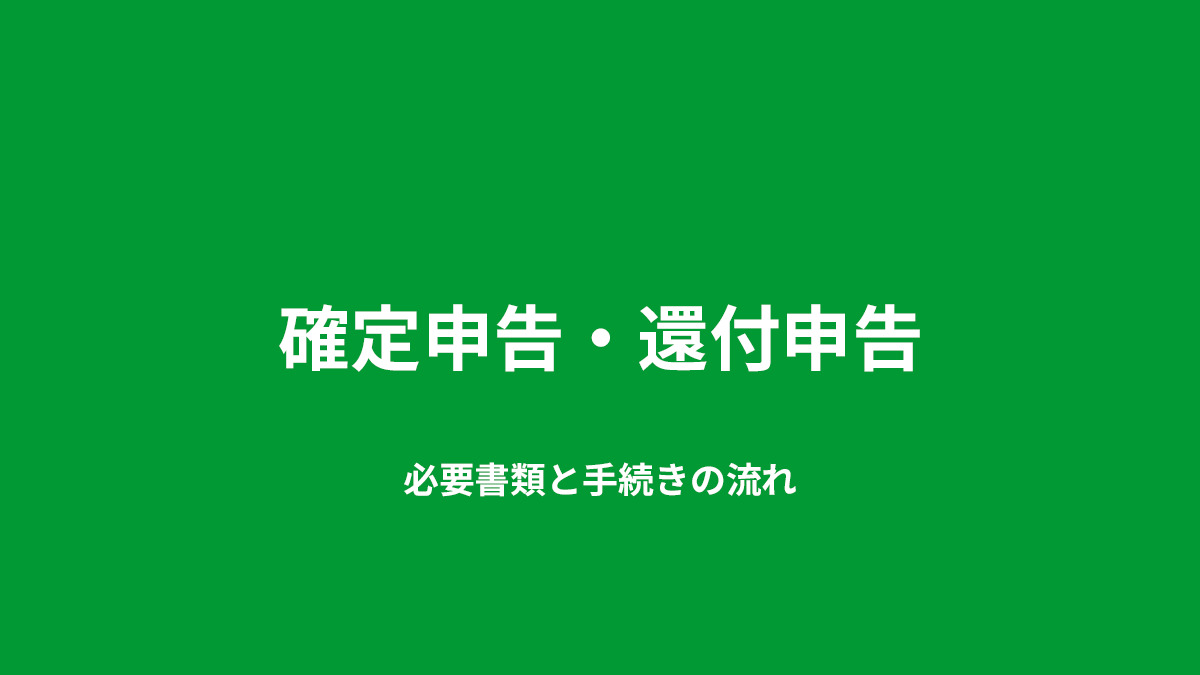
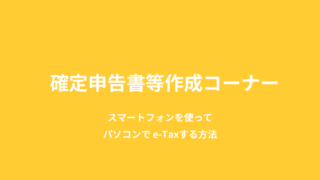
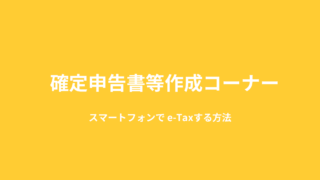
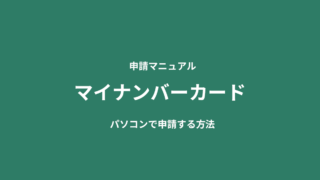
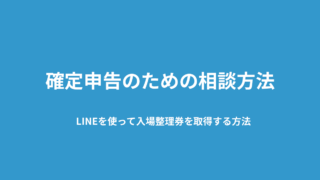

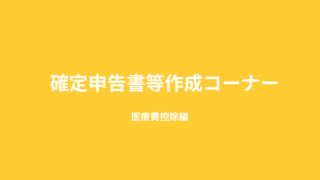


コメント